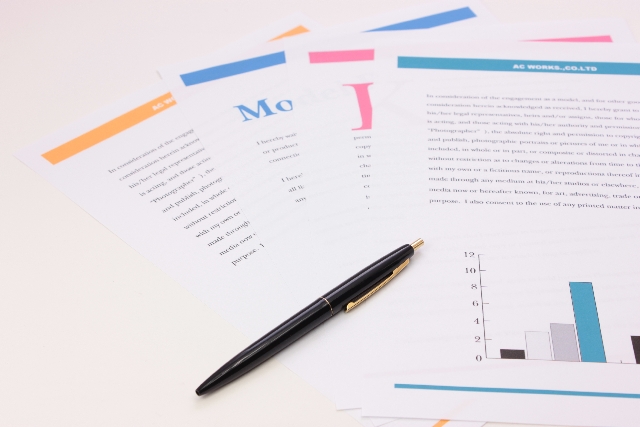


先日雇用保険について質問した続きで教えていただきたく再度投稿します。
次のどのパターンでも同じように失業保険の延長手続き、受給ができることは教えていただき解決しました。ありがとうございました。
→自己都合で退職して失業給付の申請をし、待機中に妊娠が発覚した場合
→自己都合で退職したのち妊娠し、短期間の雇用保険に加入できない仕事をしたあとの申請
→妊娠を理由に退職し、そのあと短期間の雇用保険に加入できない仕事をした後の申請
まだどのパターンになるかわからないので各パターン、どのような手順で手続きをすればいいか教えてください。
頭がよくないので同じようなことをまた聞いているかもしれません。すみません。
よろしくおねがいいたします。
次のどのパターンでも同じように失業保険の延長手続き、受給ができることは教えていただき解決しました。ありがとうございました。
→自己都合で退職して失業給付の申請をし、待機中に妊娠が発覚した場合
→自己都合で退職したのち妊娠し、短期間の雇用保険に加入できない仕事をしたあとの申請
→妊娠を理由に退職し、そのあと短期間の雇用保険に加入できない仕事をした後の申請
まだどのパターンになるかわからないので各パターン、どのような手順で手続きをすればいいか教えてください。
頭がよくないので同じようなことをまた聞いているかもしれません。すみません。
よろしくおねがいいたします。
事前に知っておきたいお気持ちもわからないではないですが…。
自分のケースに関係ない余計な知識は誤解や間違いの元です。ましてや、元々雇用保険の知識がおありでないわけですし。
ですから、実際にそのような状態になられてから、手続きについての詳細はハローワークでご自分でお尋ねになったほうが良いと思いますよ(^^)
そのときに、他に聞いておきたいことを聞けばいいんだし。手続き後の流れとか。
自分のケースに関係ない余計な知識は誤解や間違いの元です。ましてや、元々雇用保険の知識がおありでないわけですし。
ですから、実際にそのような状態になられてから、手続きについての詳細はハローワークでご自分でお尋ねになったほうが良いと思いますよ(^^)
そのときに、他に聞いておきたいことを聞けばいいんだし。手続き後の流れとか。
失業保険についてです。
昨年7月に妊娠を理由に退職しました。
延長の手続きも済ませ11月に出産して、私が無知で簡単に手当てを貰えると思っており、延長の解除をしてしまいました。
子供も
小さいですし、働く気はありません。
何回もハローワークに足を運んでいくのも難しいです…
そこで、解除してしまったのをまた延長はできないでしょうか?
初回説明会・認定日もまだ行っていません
読みにくい文書ですが…ご存知の方お願いします
昨年7月に妊娠を理由に退職しました。
延長の手続きも済ませ11月に出産して、私が無知で簡単に手当てを貰えると思っており、延長の解除をしてしまいました。
子供も
小さいですし、働く気はありません。
何回もハローワークに足を運んでいくのも難しいです…
そこで、解除してしまったのをまた延長はできないでしょうか?
初回説明会・認定日もまだ行っていません
読みにくい文書ですが…ご存知の方お願いします
質問文の読み落としがあり、失礼致しました。他にも同じ悩みを抱えている女性の方は過去、現在を問わずに沢山いますし、ハローワークへも同じ相談を受ける例は日々あるはずです。早めの方が良いので、明日にでもハローワークにお電話をしてみて下さい。専門の担当者から正確な説明を受ける事が第一です。
ハローワークの者ではありませんので、確実性はお約束出来ませんが、基本的に引き続き働く意志がないと受給資格にはならないです。受給中も就職活動をして認定日ごとに活動実績を申告する必要があります。
質問者様の場合は出産を控えておられる為という事情がございますので、恐らくは医師の診断書を提出する事により別な形で受給出来る可能性はあります。
詳細は管轄のハローワークにお問い合わせしてお尋ね下さい。詳細な説明を頂けると思います。
ハローワークの者ではありませんので、確実性はお約束出来ませんが、基本的に引き続き働く意志がないと受給資格にはならないです。受給中も就職活動をして認定日ごとに活動実績を申告する必要があります。
質問者様の場合は出産を控えておられる為という事情がございますので、恐らくは医師の診断書を提出する事により別な形で受給出来る可能性はあります。
詳細は管轄のハローワークにお問い合わせしてお尋ね下さい。詳細な説明を頂けると思います。
失業保険の給付を受ける際の「雇用保険加入期間」について。
今度、会社の閉鎖という事で会社都合として失業する事が決まりました。
ちょうど、産休予定にあたる期間だったので、早急に給付延長手続きをする予定でいます。
そこで疑問に思ったのはその失業保険の給付期間についてです。
現職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は3年半となり、それだけで判断すると、「90日間の給付」(30歳)。
しかし、前職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は2年半あり(その時は自己都合)、また前の職場から現職場就職の間は1カ月、その際の失業保険などの申請は一切していません。
この場合、失業保険の給付期間は、前職場から通算することは可能ですか??
加入期間5年以上だと、給付期間が一気に「180日間」となり、これから赤ん坊を抱えて職探しするのにあたって、長い求職期間を覚悟していますので私自身にとって大きな問題となり、ぜひ質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
今度、会社の閉鎖という事で会社都合として失業する事が決まりました。
ちょうど、産休予定にあたる期間だったので、早急に給付延長手続きをする予定でいます。
そこで疑問に思ったのはその失業保険の給付期間についてです。
現職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は3年半となり、それだけで判断すると、「90日間の給付」(30歳)。
しかし、前職場での就業期間(=雇用保険加入期間)は2年半あり(その時は自己都合)、また前の職場から現職場就職の間は1カ月、その際の失業保険などの申請は一切していません。
この場合、失業保険の給付期間は、前職場から通算することは可能ですか??
加入期間5年以上だと、給付期間が一気に「180日間」となり、これから赤ん坊を抱えて職探しするのにあたって、長い求職期間を覚悟していますので私自身にとって大きな問題となり、ぜひ質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
後の回答の方の通り、給付日数を算定する際の算定対象期間は、前社を退職して受給を受けずに次の会社で1年以内に雇用保険に加入すれば全て通算されます。よって今回は通算されます。
前の回答の方がかかれていたのは、受給できるかどうかをみる被保険者期間です。これは基本は離職前2年間に雇用保険をかけて、かつ11日以上出勤した月が12ヶ月ある場合(会社都合であれば1年間に6ヶ月)に受給できるというもので別ですね。
事業所の閉鎖で退職日が他の方と同じであれば会社都合になるでしょう。
前の回答の方がかかれていたのは、受給できるかどうかをみる被保険者期間です。これは基本は離職前2年間に雇用保険をかけて、かつ11日以上出勤した月が12ヶ月ある場合(会社都合であれば1年間に6ヶ月)に受給できるというもので別ですね。
事業所の閉鎖で退職日が他の方と同じであれば会社都合になるでしょう。
現在正社員で働いている既婚の女です。
退職予定です。
退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養に加入できるのでしょうか。
退職したら失業保険などももらえますよね。
収入があるとダメなんでしょうか。
基準とかあれば教えて下さい。
退職予定です。
退職したらすぐに旦那さんの社会保険の扶養に加入できるのでしょうか。
退職したら失業保険などももらえますよね。
収入があるとダメなんでしょうか。
基準とかあれば教えて下さい。
詳細については健康保険によって違いますのでご確認を。
妊娠が理由での退職であれば、失業給付はもらえません。
退職後収入が無いのであれば扶養に入れるかと思います。
(退職以前の収入は関係ありません)
健康保険によっては、今後収入が無いこと(妊娠のため働かないこと)の証明として、母子手帳や離職票の提出が必要になるかと思います。
失業給付を貰っている間は、日額が3612円以上の場合は扶養に入れません。
妊娠が理由での退職であれば、失業給付はもらえません。
退職後収入が無いのであれば扶養に入れるかと思います。
(退職以前の収入は関係ありません)
健康保険によっては、今後収入が無いこと(妊娠のため働かないこと)の証明として、母子手帳や離職票の提出が必要になるかと思います。
失業給付を貰っている間は、日額が3612円以上の場合は扶養に入れません。
関連する情報